抵当権つき不動産のリースバックの流れとは?抹消の方法や費用、注意点を解説

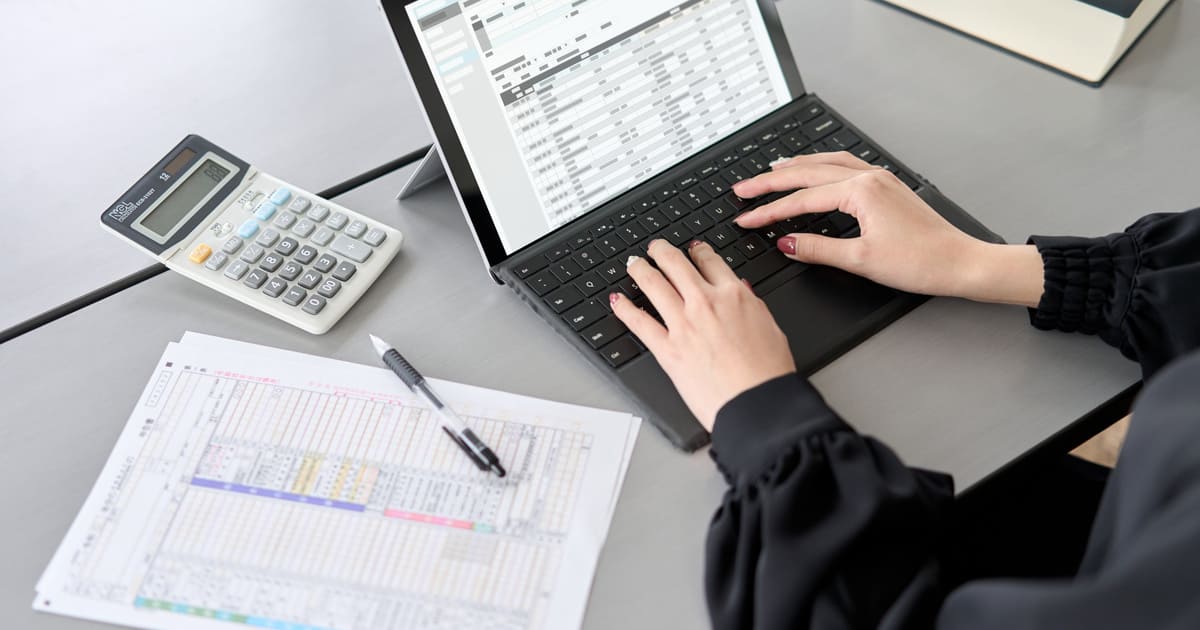
リースバックでは、所有している不動産を売却したあとに賃貸に切り換えますが、土地や物件の売却時にはさまざまな税金が課されます。
リースバックを利用するうえで、税金の負担は最終的に手元に残る金額にも影響するため、どれくらいの税金が引かれるのかが気になるという方も多いのではないでしょうか。
また、特定の条件を満たせば、節税をして税負担を軽くすることも可能です。
この記事では、リースバックにかかる税金の種類と計算方法、節税の方法について解説します。
リースバック利用時に発生する税金には、以下の種類があります。
以下では、それぞれの税金の特徴や納税方法について解説します。
印紙税とは、契約書を締結する際にかかる税金のことで、契約書に収入印紙を貼って納税します。
不動産の売買契約の契約書には、収入印紙を貼る必要があるため、自動的に印紙税を納税することになります。
リースバックを利用する際、住宅ローンの残債がある場合には、抵当権を抹消する必要があります。
登録免許税は、抵当権抹消の際にかかる税金です。
抵当権抹消の際には、不動産1つにつき1,000円の登録免許税がかかります。

固定資産税は、1月1日時点で不動産を所有している人が納税する必要があります。
そのため、1月2日にリースバック会社に不動産を売却した場合には、1月1日時点で不動産の持ち主であった売り主側に固定資産税の支払い義務が発生します。
譲渡所得税とは、不動産の売却益に対してかかる税金です。
譲渡所得は、不動産売却で得た利益のことを指しており、利益の額に応じた税額を納税する必要があります。
ただし、譲渡所得がマイナスになった場合には、譲渡所得税はかかりません。
基本的にマイホームの売却であれば消費税は発生しませんが、自身の居住以外を目的とする物件を売却する場合には、消費税がかかります。
リースバックにおいては、自身が住み続ける目的で利用する方がほとんどであるため、あまり気にする必要はないでしょう。
前述のとおり、リースバックの利用にあたってはさまざまな税金がかかります。
そのため、それぞれどれくらいの金額になるのかを計算しておくと安心です。
以下では、リースバックにかかる税金の計算方法について解説します。
印紙税を計算する際には、以下の表を参考にしてみてください。
| 契約書に記載する売買金額 | 印紙税 | 軽減税額 | 総額 |
| 1万円未満 | 200円 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 | 非課税 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 | 4万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 | 4万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 | 8万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 | 12万円 |
| 金額の記載がない場合 | 200円 | 200円 | 非課税 |
印紙税の軽減税率が適用されるのは、2024年3月31日までとされていましたが、期間が延長され、2027年3月31日まで適用されるようになりました。
譲渡所得は、「譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用」で求められます。
この計算式で用いられる数値を、それぞれ解説すると、以下の通りになります。
譲渡所得税は、譲渡所得に税率をかけた値になります。
譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間によって以下のように異なります。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 20.63% | 9% |
| 長期譲渡所得 | 5年越え | 15.315% | 5% |
税率を下げたい場合には、所有期間が5年を超えてから不動産を売却した方がよいでしょう。
譲渡所得税の金額を、簡易的な計算表にまとめました。
以下は、短期譲渡所得の場合の計算表です。
| 課税譲渡金額 | 所得税 | 住民税 | 譲渡所得税 |
| 1,000万円 | 206.3万円 | 90万円 | 296.3万円 |
| 2,000万円 | 412.6万円 | 180万円 | 592.6万円 |
| 3,000万円 | 618.9万円 | 270万円 | 888.9万円 |
| 5,000万円 | 1031.5万円 | 450万円 | 1481.5万円 |
| 7,000万円 | 1444.1万円 | 630万円 | 2074.1万円 |
次に、長期譲渡所得の場合の計算を見ていきましょう。
| 課税譲渡金額 | 所得税 | 住民税 | 譲渡所得税 |
| 1,000万円 | 153.15万円 | 50万円 | 203.15万円 |
| 2,000万円 | 306.3万円 | 100万円 | 406.3万円 |
| 3,000万円 | 459.45万円 | 150万円 | 609.45万円 |
| 5,000万円 | 765.75万円 | 250万円 | 1015.75万円 |
| 7,000万円 | 1072.05万円 | 350万円 | 1422.05.万円 |
譲渡所得税を計算する場合には、ぜひ参考にしてみてください。
リースバックで消費税が非課税になるケースには、以下の場合が当てはまります。
続いて、それぞれのケースについて詳しく解説します。
不動産売買では、基本的に土地は非課税とされています。
そのため、個人・法人を問わず、土地を売却する場合には、消費税がかからないと覚えておきましょう。

一般的に物件を売買する場合には消費税がかあかりますが、例外として個人がマイホームを売却する場合には消費税がかかりません。
ただし、居住用の物件であっても、所有者が法人名義の場合には消費税がかかる点に注意しましょう。
リースバック後の買い戻しを検討している方は、買い戻し時に発生する税金についても理解しておきましょう。
不動産を買い戻す際にかかる税金は、以下の3種類です。
続いて、それぞれの税金について詳しく解説します。
リースバックの買い戻しの際にも、契約書を締結するため、印紙税がかかります。
そのため、事前に印紙税額を調べておくとよいでしょう。
不動産の所有権を書き換えるには、登録免許税がかかります。
買い戻しの際には、売却時と同様、所有権移転登記が必要となることから登録免許税の納税が必須です。
売買した不動産の価格によって異なりますが、不動産を売却して利益がでると、その利益に対して不動産取得税がかかります。
リースバックにかかる税金にはさまざまなものがありますが、なかには節税ができるものもあります。
具体的には、以下のような制度が活用できるでしょう。
続いて、それぞれの節税方法について詳しく解説します。
マイホームを売却する場合、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けられます。
譲渡所得から3,000万円の特別控除を引くと、譲渡所得税額の軽減や非課税につながる可能性があるため、居住用財産譲渡の3,000万円特別控除を受けられるとよいです。
居住期間によって、税率が軽減される場合があります。
不動産の保有期間が10年を超えると、譲渡所得が6,000万円を超える場合に、居住用財産譲渡の3,000万円特別控除よりも軽減される税率が大きくなることもあります。
マイホームの売却によって得た利益がマイナスの場合、マイナス分をほかの所得からマイナスできることがあります。
損益通算及び繰越控除の特例を利用するには、「不動産の住宅ローン残債が売却価額より大きい」や「譲渡した年の1月1日時点で所有期間が年を超えている」などの要件を満たす必要があります。
汐留プロパティでは、リースバックをはじめとする不動産事業を幅広く手がけているため、お客様のご状況やご希望に応じて最適なプランをご提案することが可能です。
さらに、対応可能エリアは全国となっており、最短即日の買取にも対応しております。
リースバックをご利用したい方はもちろん、リースバックとリバースモゲージでお悩みの方、他社での査定に不安がある方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
