リースバックはオーバーローンだと絶対にできない?例外的にできるケースと注意点


不動産のリースバックを検討している方のなかには、所有する物件や土地には抵当権がついているため、リースバックはできないと諦めている方もいるのではないでしょうか。
たしかに、原則として抵当権つきの不動産はリースバックできませんが、例外的に認められるケースもあります。
また、抵当権を外してリースバックしたいと考えている方は、抵当権抹消の流れについて理解しておく必要があります。
この記事では、抵当権つき不動産をリースバックする方法や手続き、注意点について解説します。
抵当権とは、住宅ローンを利用して不動産を購入する場合に発生する、購入する不動産を金融機関が担保にできる権利です。
抵当権を設定することにより、債務者から住宅ローンが返済されなかった場合、金融機関はその不動産を競売にかけて売却し、売却代金から住宅ローンの回収を図れます。
つまり、抵当権は債権者を守るための権利だといえます。
抵当権のついている不動産は、原則として売却できません。
もし、抵当権のついている不動産を売却する場合には、金融機関の許可が必要です。
そもそも抵当権のついている不動産は、債務者が住宅ローンの支払いができないと競売にかけられるおそれがあり、買い手がつきにくいことからも抵当権を外して売却するのが一般的です。
抵当権のある不動産をリースバックすることは可能ですが、条件や状況によってできるかどうかが異なります。
以下では、「アンダーローン」と「オーバーローン」の2パターンに分けて、リースバックができるのかを解説します。
アンダーローンとは、住宅ローンの借入額が不動産の価値を下回っている状態を指します。
たとえば、住宅ローンの残債が4,000万円で、不動産の売却価格が5,000万円のような状況が考えられます。
この場合、抵当権のある不動産をリースバックすることは比較的容易です。
なぜなら、不動産の売却代金が借入金額を上回るため、売却によってローンを完済できるからです。
アンダーローンの場合には、金融機関の同意を得たうえで、抵当権抹消の手続きを行い、不動産を売却します。
オーバーローンとは、借入額が不動産の価値を上回っている状態を指します。
たとえば、住宅ローンの残債が3,000万円で、不動産の売却価格が2,000万円のような状況が考えられます。
この場合、リースバックを行うのは難しいでしょう。
売却代金がローン残高を下回るため、金融機関には全額回収できないリスクが生じます。
そのため、金融機関にリースバックを認められない可能性が高いです。

オーバーローンの状態で不動産を売却する場合、任意売却という方法がとられることがあります。
任意売却とは、競売を避けるために、債権者と協議のうえで市場価格に近い価格で不動産を売却する方法です。
金融機関との調整が必要ですが、適切な売却計画を立てることで、オーバーローンの状態でも売却が可能となる場合があります。
しかし、任意売却自体が成立しづらいことや、任意売却をする人に家賃の支払い能力がないと判断される可能性があることから、任意売却でのリースバックは難しい傾向にあります。

抵当権のある不動産をリースバックする際には、以下の流れで進めます。
以下では、それぞれのステップについて解説します。
はじめに、リースバックを提供する不動産会社と契約を結びます。
この契約では、不動産の売却価格や賃貸条件、契約期間などが定められます。
リースバックの契約を結ぶ際には、将来的な賃料や契約の更新条件についても詳しく確認し、納得のいく条件で合意することが重要です。
また、リースバックの目的や長期的な計画を明確にし、慎重に判断するようにしましょう。

次に、住宅ローンの借入先である金融機関に対し、リースバックをする意向を通知します。
通知の際には、リースバックにあたっての各種条件や売却後の返済計画についても説明します。
金融機関の方でもリースバックにあたって準備が必要なため、期間に余裕を持って、通知しましょう。
抵当権のついた不動産をリースバックする場合には、司法書士に抵当権抹消手続きを依頼します。
リースバックの契約をスムーズに進めるうえでは、いつまでに抵当権の抹消手続きを済ませればいいかを確認しておき、司法書士に対して希望のスケジュールとして伝えておくと安心です。
抵当権抹消には、以下の書類が必要です。
登記識別情報通知書は、法務局の窓口か郵送で受け取れます。
登記識別情報通知書以外の書類は、住宅ローンの借入先の金融機関で受け取りましょう。
最後に、抵当権の抹消手続きをおこない、抵当権が抹消されたら不動産を売却します。
そして、不動産が売却できたら、売却代金を使って住宅ローンを完済します。
抵当権の抹消には、以下の費用がかかります。
次に、抵当権の抹消にかかる費用をそれぞれ詳しく解説します。
抵当権抹消にかかる費用のうち、もっとも主要なものが登録免許税です。
登録免許税は、法務局に対して抵当権抹消登記を申請する際に支払う税金であり、税率は法律で定められています。
2024年6月現在の税率は、抵当権抹消1件あたり1,000円です。
複数の抵当権が設定されている場合、それぞれの抵当権について登録免許税が発生します。
たとえば、売却する不動産が一戸建ての場合には、土地と建物の両方の抵当権を抹消する必要があり、登録免許税は2件分の2,000円がかかります。
抵当権抹消手続きを円滑に進めるためには、事前に不動産の登記内容を確認する必要があります。
この際にかかる費用が事前調査費用です。
不動産の登記内容の確認には、登記事項証明書を発行する方法と、登記情報提供サービスを利用する方法があります。
それぞれの方法で登記内容を確認する際の費用は、以下のとおりです。
| 確認方法 | 費用 | |
| 登記事項証明書の発行 | 法務局の窓口で取得 | 土地1筆あたり600円 |
| ネットで取得 | 土地1筆あたり500円 | |
| 登記情報提供サービスの利用 | 土地1筆あたり332円 | |
ただし、登記情報提供サービスを利用する場合には、手元に登記事項証明書を残せない点に注意しましょう。
抵当権抹消確認費用は、抵当権を問題なく抹消できているかを確認するための費用です。
事前調査と同様、登記事項証明書を発行する方法と、登記情報提供サービスを利用する方法があります。
費用についても、事前調査で不動産の登記内容を確認する場合と同じです。
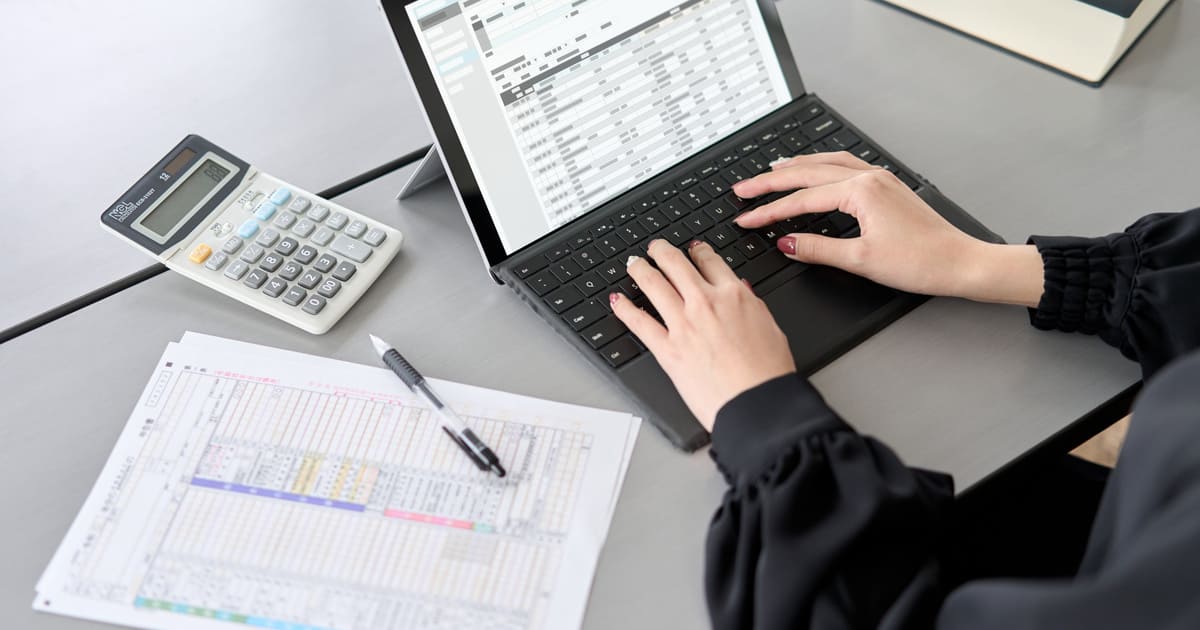
リースバックをおこなうには、抵当権抹消以外にも以下のような条件があります。
まず、アンダーローンでなければ抵当権を抹消できず、基本的にリースバックはできません。
さらに不動産の名義人が複数人いる共有持分をリースバックするには、名義人全員の同意が必要なことにも注意しましょう。
また、リースバックでは、不動産売却後に家賃の支払いが発生するため、家賃の支払い能力が認められる必要があります。

抵当権抹消手続きをスムーズに進めるためには、以下の注意点があります。
続いて、それぞれの注意点について詳しく解説します。
抵当権抹消手続きをする際に、氏名や住所が変更されている場合、変更手続きを同時におこなう必要があります。
たとえば、結婚や離婚による氏名変更や、引越しによる住所変更などがあれば、登記簿上に反映させる手続きが求められます。
反映手続きを怠ると、抵当権抹消申請が受理されないことがあるため、事前に変更手続きを済ませておくことが重要です。
抵当権抹消手続きには、さまざまな書類が必要となりますが、これらの書類には有効期限が設定されている場合があります。
たとえば、登記事項証明書は、発行から3ヶ月以内に提出する必要があります。
期限が過ぎた書類を提出すると、手続きが遅れる原因となるため、各書類の有効期限を確認し、適切なタイミングで書類を準備することが求められます。
汐留プロパティでは、リースバックをはじめとする不動産事業を幅広く手がけているため、お客様のご状況やご希望に応じて最適なプランをご提案することが可能です。
さらに、対応可能エリアは全国となっており、最短即日の買取にも対応しております。
リースバックをご利用したい方はもちろん、リースバックとリバースモゲージでお悩みの方、他社での査定に不安がある方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
